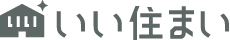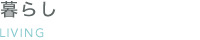「新生活の第一歩!引っ越しのあいさつはどうする?あいさつの意義やおすすめの手土産を解説」
2025.03.27
4月。住まいを引っ越して新しい生活を始める方にとっては、大忙しの時期ですね。新居での生活を円滑にスタートさせるためには、近隣へのあいさつが欠かせません。今回のいい住まいでは、引っ越しのあいさつをするべきかどうか、あいさつの意義を考え、あいさつのタイミングやお勧めの手土産についてご説明します。
引っ越しのあいさつはするべき?

引っ越しのあいさつはするべきか?と問われたら、できる限りした方が良いと答えます。マンションコミュニティーの新しいメンバーとなれば、今後お世話になったり災害時には助け合ったりする場面があるかも分かりません。昔からいわれる通り、〝向こう三軒両隣〟に家族全員で出向いてあいさつをするのがマナーと理解しておくと良いでしょう。
あいさつ一つで最初の印象が良くなるものですが、近年では「防犯上の理由からあいさつしたくない」との考え方があります。特に女性の一人暮らしの場合は不安を感じるかもしれません。近隣の中には「煩わしいから来なくて良い」とあいさつを拒む方がいることもあります。しかし、ほとんどの場合は気持ちよく受け入れてもらえます。家族構成を知られたくない時は、不動産会社の担当者に同行してもらうことも一案です。住む地域の風習や状況に合わせて判断しましょう。
入居前にマンションの管理員さんから共用施設の説明を受ける機会があれば、これまでの入居者がどうしていたのか、尋ねてみるのも良いかもしれません。
引っ越しのあいさつをする意義

家族で引っ越しのあいさつをすることは、次のような意義があります。
近隣トラブルの予防
マンションで最も多いトラブルが足音などの生活騒音です。引っ越してすぐ家族が全員そろってあいさつに伺うことで親しみを感じられ、たとえ迷惑を掛けることがあっても穏便に収めてもらえるかもしれません。あらかじめ「早朝に帰宅する夜勤シフトがあります」「子どもが夜泣きをしたり走ったりするかもしれません」などと伝えておくことで、トラブルの予防につながるでしょう。「顔見知りの子の足音なら少しは我慢できる」という声もあるのです。
地域の情報が得られる
あいさつをきっかけに、地域の情報を教えてもらえることがあります。特にゴミ出しルールや自治会・町内会の情報は、知らずにいると周りに迷惑をかけてしまうことがあります。最寄りの内科医・外科医の場所を聞いておくと、いざという時にあわてずに済みます。
安心感が生まれる
近隣に知っている人がいることで、何かあったときに助け合える関係を築きやすくなり、新しいコミュニティーへ参加することに安心感が生まれます。迎える方々も「新しく引っ越してくるご家族はどんな人だろう」と気にしているかもしれませんね。
あいさつの範囲、あいさつのタイミング
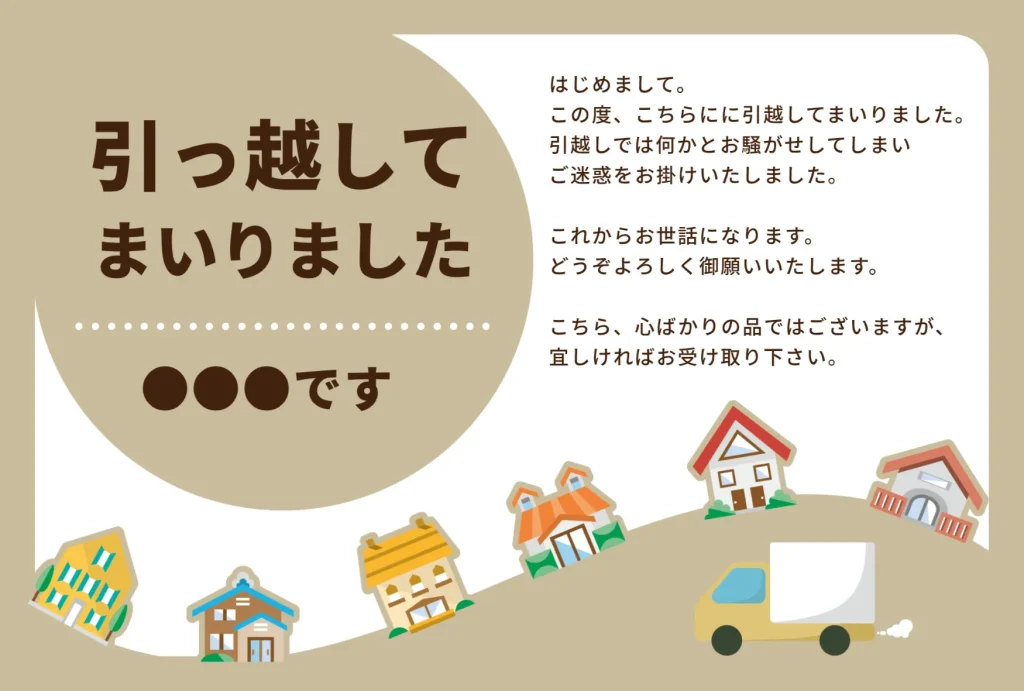
実際にあいさつに伺う先は、どのくらいの範囲でしょうか。
マンションの場合はまず管理員さんや大家さんにあいさつしましょう。そして〝向こう三軒両隣〟のマンション版として、両隣の方と、すぐ上と下の合計4軒に伺います。
あいさつのタイミングは、引っ越しの前日までに「今度入居する○○です。ご迷惑をおかけします」と伝えるようにします。これは荷物の搬入時にはどうしても騒音が出ますし、エレベーターを止めたりもするからです。入居が決まった段階で「○月○日に引っ越してきます」と伝えるのも良いでしょう。遠方からの引っ越しで事前にあいさつができない場合は、遅くとも入居後1週間以内にはあいさつに伺いたいものです。
訪問する時間は10〜12時、昼食の時間帯を避けて13〜16時台がベストです。日中に不在だった場合は、19時台までに再訪問します。不在が続く場合は、郵便受けやドアノブにメモ程度のあいさつ状と、ごあいさつの品を入れておきましょう。
手土産におすすめのもの

あいさつの際は手ぶらではなく、ちょっとした手土産を持っていくと印象が良くなります。おすすめのものは次の通りです。
- 日用品・・・タオル・洗剤・ラップなど。実用的で無駄になりにくいため、どんな家庭にも喜ばれます。
- 菓子・・・個包装の焼き菓子・和菓子など。賞味期限が長く、食べやすい個包装のものが好まれます。
- 地域の名産品・・・自分の出身地の名産品やそれまで住んでいた地域のものを持っていくと、話のきっかけになることもあります。
高価すぎるものはかえって気を遣わせてしまうため、500~1,000円程度の手土産が適切です。のし紙には忘れずに自分の名前を書いておきましょう。
まとめ
引っ越しのあいさつは必須ではありませんが、良好な近隣関係を築くための潤滑油です。特にアパートやマンションでは騒音トラブルを防ぐ意味でも、隣接する部屋と上下の部屋の方にはあいさつしておきたいもの。新しいお付き合いの第一歩、ぜひ前向きに検討してみてください。旧住まいのご近所さんにも、一言、転出のごあいさつを忘れずに。